山村暮鳥の雨に関する詩を、三作続けて紹介します。
「雨の詩」
「雨は一粒一粒ものがたる」
「驟雨の詩」
以上の三つの詩は、いずれも詩集『風は草木にささやいた』に収められています。実はこの詩集、雨が出てくる詩が意外と多くて、何と十作以上もあるのです。
どれも捨てがたいのですが、どうしても紹介したい作品だけを選びました。どうぞご覧くださいね。
山村暮鳥の雨の詩
雨の詩
雨の詩
ひろい街なかをとつとつと
なにものかに追ひかけられてでもゐるやうに驅けてゆくひとりの男
それをみてひとびとはみんなわらつた
そんなことには目もくれないで
その男はもう遠くの街角を曲つてみえなくなつた
すると間もなく
大粒の雨がぽつぽつ落ちてきた
いましがたわらつてゐたひとびとは空をみあげて
あわてふためき
或るものは店をかたづけ
或るものは馬を叱り
或るものは尻をまくつて逃げだした
みるみる雨は横ざまに
煙筒も屋根も道路もびつしよりとぬれてしまつた
そしてひとしきり
街がひつそりしづかになると
雨はからりとあがつて
さつぱりした青空にはめづらしい燕が飛んでゐた
まるで童話のような詩ですね。
暮鳥は詩人であり童話作家でもあるので、その素質が生かされている作品です。
それにしても、現実でもこのような場面に見覚えがありませんか?まるで社会の縮図を描いて、風刺しているかのようです。
大衆というものは、大雨のような災難がその身に降りかかってこないと気づけなくて、振り回されているものなんですね。雨の予兆や、雨上がりの空には、見向きもしようとしません。
この詩を読んでいると、大衆に惑わされることなく、自分の信じる道を貫きたいと感じます。
雨は一粒一粒ものがたる
雨は一粒一粒ものがたる
一日はとつぷりくれて
いまはよるである
晩餐ののちをながながと足を伸ばしてねころんでゐる
ながながと足を伸ばしてねころんでゐる自分に
雨は一粒一粒ものがたる
人間のかなしいことを
生けるもののくるしみを
そして燕のきたことを
いつのまにかもうすやすやと眠つてゐる子ども
妻はその子どものきものを縫ひながら
だんだん雨が強くなるので
播いた種子が土から飛びだしはすまいかと
うすぐらい電燈の下で
自分と一しよに心配してゐる
雨の夜に寝転んでいると、日中に活動していた時以上に、雨音がよく聴こえてきますよね。
その雨音を、暮鳥は「一粒一粒ものがたる」と表現したのですね。
一粒一粒という言葉から、どんな小さな一滴にも命が宿り、物語を秘めているだと感じられます。
人間もまさにそうですね。天から見れば人間もささやかな存在ですが、一人一人に悲しみや苦しみがあり、歴史があります。
さて、暮鳥の子どもは眠っているものの、暮鳥はなかなか寝付けないようですね。
雨音が強くなるなか、せっかく畑に蒔いた種子が土から飛び出したりはしないかと、心配しています。
昼に汗水流して働いて、夜になって休もうとしても、心はまだ土に残っていて、なかなか気が休まらない様子が伝わってきます。
それを一緒に心配している、奥様の存在が心強いですね。
生活に根ざしている、味わい深い詩です。
驟雨の詩
驟雨の詩
何だらう
あれは
さあさあと
竹やぶのあの音
雨だ
雨だ
おやもうやつてきた
ぽつぽつと大粒で
ああいい
ひさしぶりで
びつしより濡れる草木だ
びつしよりぬれろ
驟雨とは、にわか雨のこと。夏の季語に当たります。
この詩を読んでいると、瞬く間に雨がやってきて、草木をびしょ濡れにさせているのが、目にそのまま浮かぶかのようです。
晩年の詩集『雲』を思わせる息づかいで、短いながらも心に響きます。
暮鳥は久々の大雨を、「ああいい」と喜んでいますね。
強く打ちつけながらも、生物たちを育む恵みの雨だと感じられます。


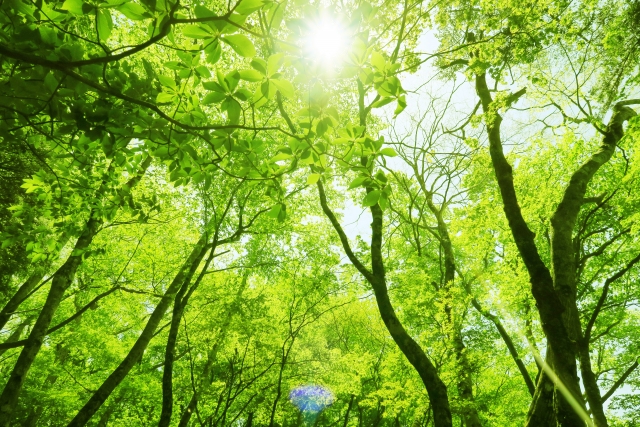

コメント